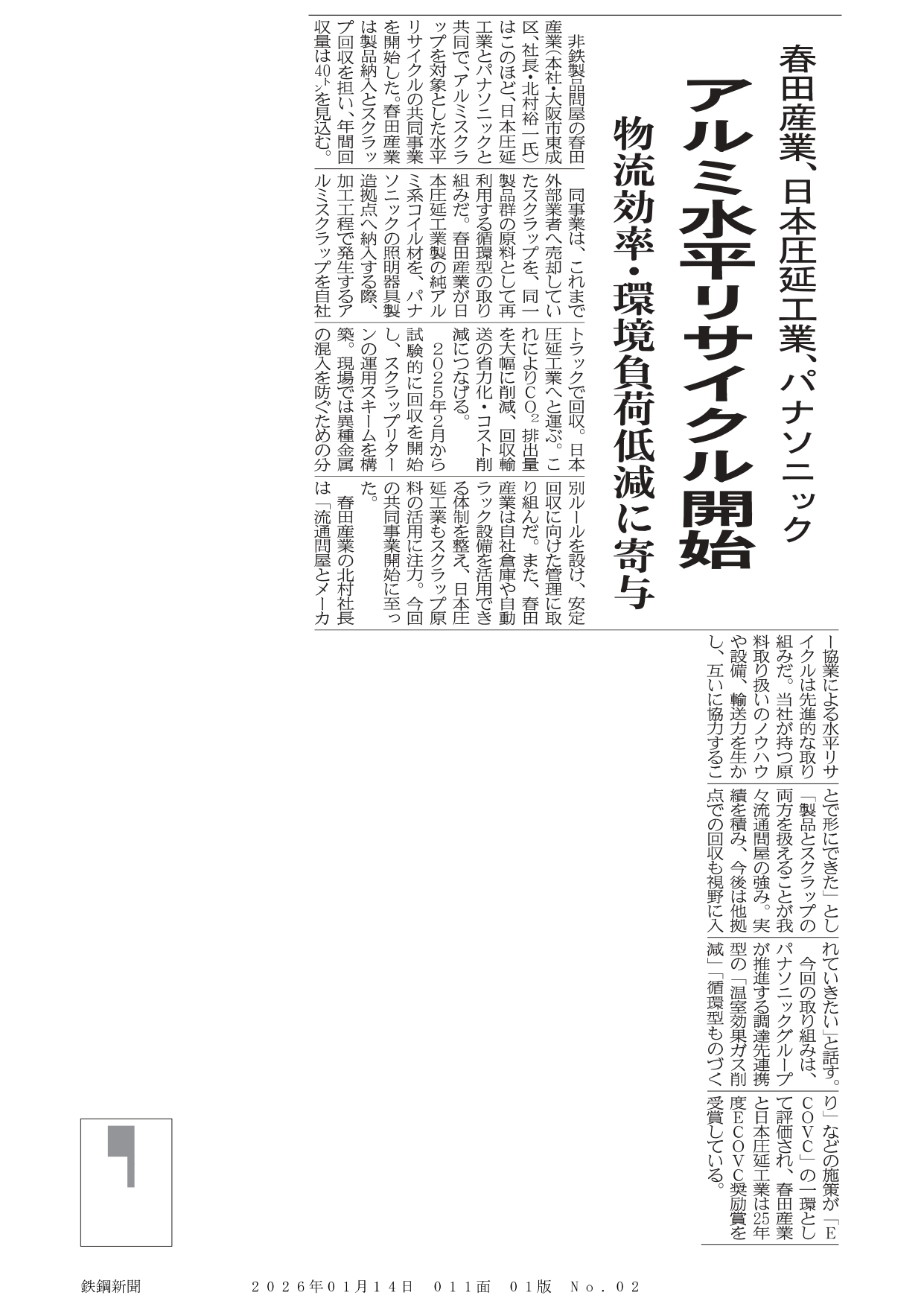連続鋳造法ができるまで
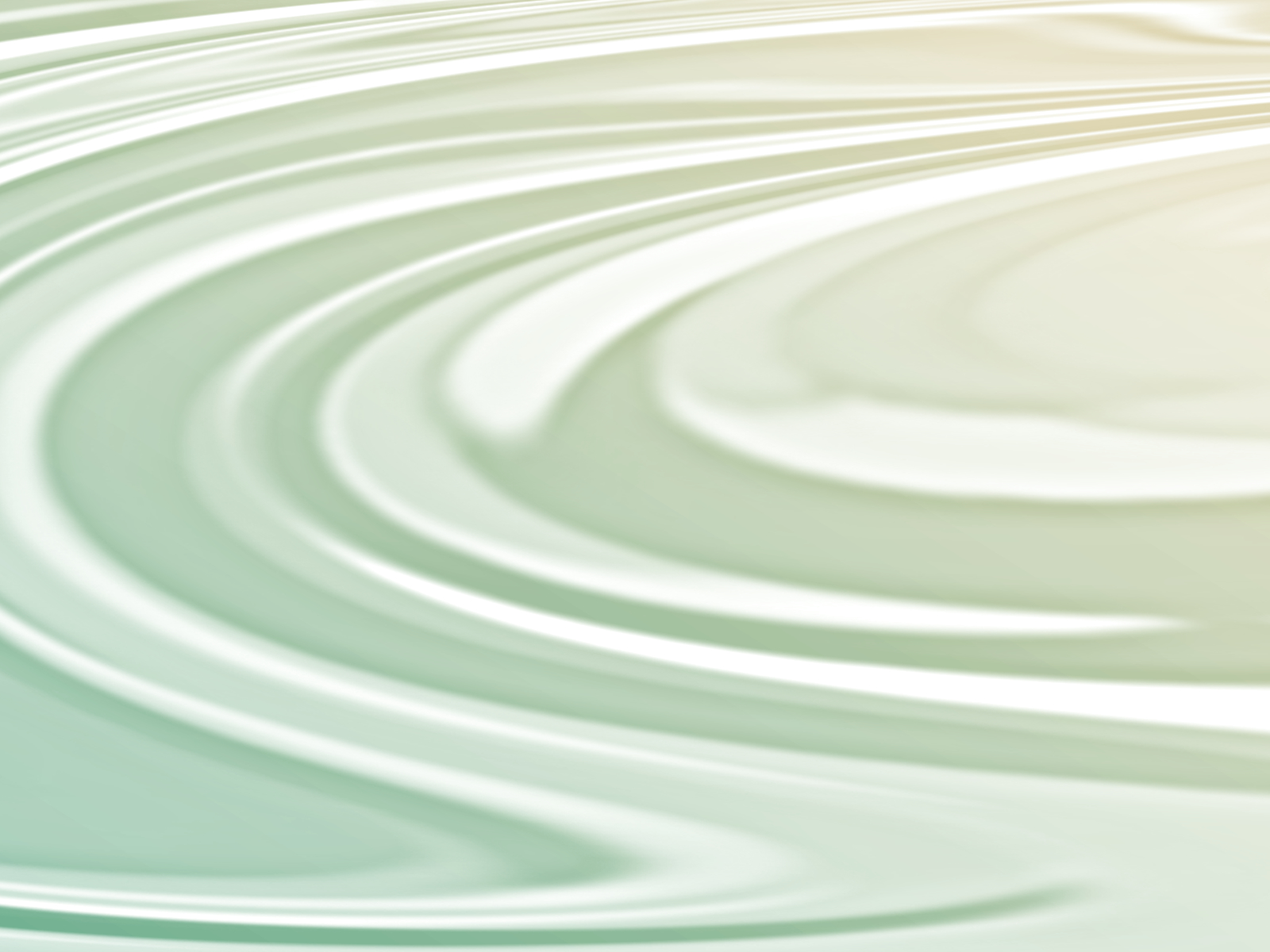
そもそも連続鋳造法とは
展伸材用素材(金属を圧延・鍛造・引抜き・押出しで形状づくりされる材料)を工業的規模で均一、大量に生産する方式として溶湯から連続的に鋳物を製造する方法です。
連続鋳造法ができる前は通常、溶湯を鋳型に流し込んで作られていました。
所要の形にしたこの鋳物にも2種類あり
・鋳塊:鋳物を圧延、押し出し、鍛造などによって加工する場合
・鋳物:鋳込んだままの状態で使用、金属が最初に受ける加工
以上があります。
では連続鋳造法ができた経緯は何かというと、
1846年にイギリスの発明家、ベッセマーが板ガラスの製造法から着想を得て2つの水冷ロールの間に溶銅を流し込んで鋼鈑を製造したのがはじまりです。
その後1933年、ユングハンスが鋳型を上下に往復運動させることによって焼き付き防止と冷却効果を大きくしたのが工業用としての始まりになり、プロセスの改良が進められ1950年代に連続鋳造法として確立しました。
連続鋳造法のメリット等の詳細や日本圧延工業の連続鋳造については下記ページになります(^^♪
https://www.nichiatu.co.jp/media/alminium/a5